本ページは、ダーツを投げるための体の動かし方について解説していきます。
10個目でようやくダーツを投げることができます。お待たせしました。ここからが本番です。というのもここが一番知りたかったのではないでしょうか。
ここから、あなたのダーツの考え方が飛躍的に向上します。すこし長丁場になると思うので、ぜひご覧ください
結論:「再現性」

まず、一番最初に覚えておいてほしい言葉は、「再現性」です。
再現性とは
- もう一度同じように投げることができますか?
- 昨日できたことが今日もできますか?
という意味です。
ダーツは、明日になったらダーツボードが上下動したり、距離が変わったりするなどということはありません、明日もほとんど同じ条件です。
つまり、明日も明後日もブルや20トリプルなどを同じ場所を狙う必要があります。それができないと、スコアが上がることはありません。 昨日できたこと、今日、明日できるようにしておかないといけないのです。
逆に3本とも同じように投げることができれば、それは再現性があるといえるでしょう。 それができるならどんなフォームでもいいのです。 世の中のトッププロという方々のフォームはすべてバラバラです。正解等ありません。
まずは一回投げてみよう
トッププロのフォームがバラバラだといっても、その人の中での正解が必ずあります。つまり、あなたにとっての正解は必ずあります。
もう少しいうと、あなたの体に適した正解は絶対にあります。
まずは自分の投げ方、現在地を知るために投げてみましょう。ブルに向かって投げてみてください。 その時に、必ずやってほしいことがあります。絶対に投げているフォームの動画を撮ってください。 撮影したら次に行きましょう。
投げ方がわからない場合は上の動画を参考にしてみてください!
再現性を実現するための考え方3つ

「再現性」という言葉に関して、ダーツの勉強熱心なあなたはちょこちょこ聴いてきていると思います。ただ、再現性を得るために何をすればいいのかわからないという話もダーツを教えていて感じます。
そこで、ここでは再現性を得るために必要な考え方を紹介します。
1.ちゃんとマイダーツを使っていますか。

マイダーツというと少し語弊があります。いつもと同じダーツを使っていますか?
同じダーツを投げないと感覚が変わるのは当たり前です。自分にとっての相棒を使用して、決めて、投げましょうどれがおすすめのダーツかわからない人は、前の記事にマイダーツの選び方を紹介していますので、ご覧ください。アフィリエイト界隈に革命がおこるページです。
2.投げているときに不自然な力みを感じましたか。

ダーツはそもそも力がしっかり伝われば軽い力でも飛んでいきます。「不自然な力みがある」ということは、体の制御が難しいということです。
逆に、体の思うままに、自然に、動くことで、毎日同じように動いてくれます。例えば、ご飯を食べる、お水を飲むなど、日常で毎日やることに不自然な力みがあるかどうかを思い浮かべてください。
ただ、ここで大事なのは、脱力をすることを推奨してるわけではありません。あくまでも無理している感覚があるかどうかが大事です。明日も同じように投げる手段として、あなたに最適な力加減を考えてみましょう。
申し訳ありませんが、これは感覚論です。沢山投げ込んでいるとわかります。投げていると謎にバチっとハマる一本が現れます。その感覚を再現するような動きを増やす。それがダーツです。その感覚がまだない人はもっと投げ込んでみてください。いつか現れる一本を目指して。
3.3本とも同じように投げることができていますか。
動画を見たあなたは思っているはず。こんなにも同じ動きをできていないのかと。
体を動かすプロのうちの一人、武井壮さん。上の動画で意識して体を動かすことの難しさについて語っています(9:35あたり)。
つまり、「三投同じ投げ方をするということは難しい」どころか「1回でも理想の体の動かし方をすることは難しい」ということです。
ではどうすれば、体を思った通りに動かすことができるのか。それも武井壮さんが解説してくれています。「動画を撮って客観視すること」しかないです。理想とのギャップをしっかり客観視して確認し修正する。その先にターゲットに入るフォームがわかります。
再現性を実現するための考え方

ダーツをコントロールするのではない。
自分をコントロールするのだ。
ダーツとは、そもそもどういうスポーツでしょうか。体を動かして矢に信号を伝え、その信号によって矢をターゲットに対して指すというスポーツなんです。
もっと言うと、体を動かすだけのスポーツなんです。
本当の意味で理解してください。矢をこねくり回すスポーツではないのです。つまり体を動かす方法にフォーカスする必要があります。
ダーツとは、関数である。

難しいことは分けて考えよう。
聞いたことがない人は、本日覚えてください。非常に役に立ちますよ!というわけで少し理系的な話をしようと思います。
皆さん、関数ってご存じですかね? わからなくてもわかりやすく説明するので聞いてください。わかる人に先に言っておくと、f(x)みたいなやつです。
これはどういう意味か。
「xという信号が与えられたときに、そのxに従って答えが出力される」という考え方です。
ダーツで言う出力とは、ダーツボードのターゲットにあたるかどうか、近いかどうか、です。
そして、ダーツに関しては、変数が一つではないんです。
- ダーツの持ち方
- 姿勢・立ち方
- 立つ場所
- 腕の振り方
- ダーツボードへの距離
などなど。もしかしたら、目から入る情報も含まれているかもしれません。
つまり、f(x)はなく、f(x,y,z)というような多変数関数なんです。
さぁ。皆さんにここで質問です。f(x)と、f(x,y,z)、どっちが簡単そうですか?
そう。純粋に変数は少ないほうが、出力が安定しそうじゃないですか?
xyzのバランスを調整する作業よりも、x,yをきわめて定数に近い値にして、zだけを動かそうとするほうが楽じゃないですか?
つまり、その変数をいかに定数っぽくコントロールするか考える必要があるのです。
その変数の正体とは?
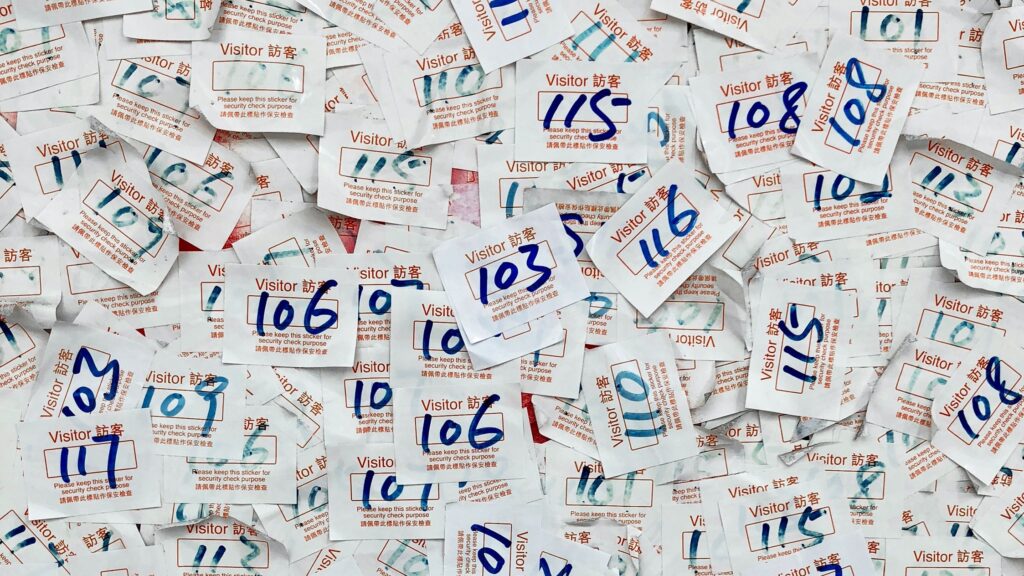
そして、その変数をコントロールする方法は何でしょうか。
難しいことは分解して考えればいいのです。
そしてその分解方法も先人たちが教えてくれてます。
この3つです。それぞれとても重要な項目ですので、1個1個別々にページを作成しています。絶対にそれも見てください。
忘れがちだけど、とても大事な考え方

スローが終わったら、それ以上ダーツになにかをしてあげることはできません。あなたがダーツに伝えた信号の出力結果を見守って上げるのみです。
なにか改善点があるとしたら、グリップ、スタンス、スローの何処かにあります。
しっかり見直して改善しましょう。
まとめ

本ページでは、最短でプロになるためのダーツフォームの考え方を紹介してきました。
再現性を実現するために必要な考え方3つ、覚えましたか?
- マイダーツを使っていますか
- 投げているときに変な力みを感じましたか
- 3本とも同じように投げることができているか
そして、わかりづらいことは分解して考える必要があるということも紹介しました。
これは、ダーツに限らず、人生に応用可能なやり方です 是非覚えて帰ってください。
次に見てほしいページは、グリップ完全解説になります。続けてご覧ください。
以上となります。本ブログでは、ダーツのことを今後も発信していきます。
これからも応援よろしくお願いします!
超余談

「分解して考える」で言うと、岡田斗司夫の悩みについての話 悩みのるつぼという話がとても面白いです。
全部面白くて、世の中の全員にためになるので聞いてほしいんですが、 特に、21:25からの部分が今回関係あります。
「この動画からわかることは、 悩みの解決方法だ! 本質を見極める力だ。」
とか、見る人にとってこの動画の学びは別視点かもしれません。
ただ、この動画とダーツとの共通点は
「書き出し→分類→自分の今後コントロールできる部分に注力する。」
これぞ、ダーツ学。ダーツをすることで、人生をよりよくすることができます。 ダーツって本当に人生にとって有意義な趣味ですよね。
以上です。ありがとうございました。




コメント